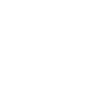
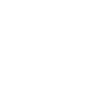
News
2025.09.25
東京大学で行われた行動モデル夏の学校に研究室学生11名+浦田で参加してきました。
行動モデル夏の学校は「行動モデル夏の学校は、土木・建築・都市を専門に学ぶ全国の大学院生や若手研究者、エンジニア、政策担当者を対象に、都市計画と交通計画で用いられている離散選択モデルの基礎と専門知識の修得を目的に開講」されています。今年も、13(?)大学・20チーム以上・110人超の参加があり、大変盛況でした。
We participated in the Summer School on Behavioral Modeling held at the University of Tokyo, with 11 students from our lab and Prof. Urata.
The Summer School on Behavioral Modeling is designed for graduate students, early-career researchers, engineers, and policymakers specializing in civil engineering, architecture, and urban studies. Its goal is to provide foundational and advanced knowledge of discrete choice models used in urban and transportation planning.
This year’s program was a great success, with over 110 participants from more than 13 universities and 20 teams.

夏の学校全体としては,機械学習・深層学習系の手法が浸透しつつることを実感しました.2018年頃から夏の学校の講義でも取り扱っているトピックですが,社会の状況が変わって使いやすくなっていることもあり,実際に色々な交通現象・予測に使えるようになってきたのかなと感じます.”行動モデル”夏の学校ではありますが,離散選択モデルの明瞭さに対して,機械学習・深層学習系の予測可能性の高さをどう捉えるかは切り離せない時代になりましたので,良い変化かなと思います.
交通手段選択系,手段分担に関する伝統的な政策評価の発表はだいぶ少なくなってきた印象があります.従前の四段階推定や,四段階推定をなぞるようなPPの活用方法ではなく,柔軟な活用方法ができることが広まりつつあるのかなと思います.2000年頃にプローブパーソン(PP)調査の雛型が始まった頃からみれば,渋谷や豊洲,去年の松山のようにPPの細かさにあう空間解像度で説明変数を用意できる時代になったこと,大きい計算量にも耐えられるような計算機が手に入るようになったこともあるかもしれません.同時に,通勤・通学がリモートで減る中で混雑体験が減って問題意識が変わっているとか,単なる離散選択モデルで効用推定してもバス問題解決しないよね,ということもあるかもしれません.こういうPPならではの特徴を生かしたアイディアを,政策・施策にどう展開するのかという点は課題ではありますが,モデルを理解する人・モデルのインプリから提案に繋げられる人を増やしていくことで課題解決に繋がるのではないかと思っています.
学生さんは,短期集中+グループで,行動モデル・データ分析・政策評価を議論する良い機会になると同時に,様々な大学の先生方や学生さんからの刺激も得たようで,大変だったと思いますが,参加して良かったなと思いました.
Other news
↑