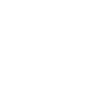
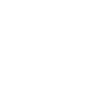
News
2025.11.11
10月1日から24日にかけて、スマートキャンパスプロジェクトの社会実験を実施しました(まだ調査・研究は続いています)。従来は駐輪場として使っていたスペースに椅子とテーブルを設置し、キッチンカーを招くなどして滞在空間を創出しました。あわせて、実験エリアでは駐輪を禁止し、自転車は手押しで通行するよう規制しました。色々な方にご協力いただき、大変ありがたかったです。

10月中盤は天気の悪い日が多かったのが、少し残念でしたが、1年間通せば、都合の良い天気ばかりではないので、そんなものかなと思います。集客という意味で見れば、滞在空間があるということに加えて、人通りがある場所でなんかやっている(特にキッチンカー)ことの影響が大きいのかなと感じました(今後の分析に要注目)。一方で、何もやっていない10月末の火曜の朝や昼も、それなりの気候であれば誰かいるという感じもあり、滞在場所として一つの選択肢に入る場所には十分になったのかなと思いました。研究室など室内に固定の居場所がある人達にとっては、室内の食堂よりも外の広がりのある空間のほうが気分転換にふさわしいというのもあるかもしれません。大学らしい場所だと感じたという声も聞きましたが、良い空間への滞在経験を大学の中で生めたことは良かったことだと思っています。

社会実験前の3A棟前

社会実験中の3A棟前
一方で、もちろん駐輪場所が減ったり、自転車通行できなかったり、駐輪・通行のしわ寄せが生じたりといった変化が生じたことも確かです。空間形成でも他のことでも、何かを変えるときに全てが良くなるということはありえず、なにかは悪化すると思います。その悪くなったことと良くなったことを比べてどうなのか、悪化した幅をどのように狭めることができるのか。そういうことを考えられるのが社会実験の意義であり、引き続き考えていきたいと思います。また、研究室内で話していましたが、一ヶ月やったことで駐輪台数が均衡したり、その中で混雑する場所が明らかになったり、椅子・机の維持管理の課題が見えてきたり、と学びも多かったなと思います。
プロジェクトにあたって、周辺をよく観察すると、違法駐輪を助長させてしまうような空間のつくり方は、(他のことも含めて)違反してもいいという心理を生んでしまう可能性があり、望ましくないだろうと思いました。同時に、幅員の狭い渡橋直後の場所に駐輪場を設けていることで急減速する自転車と、そのまま通行する自転車の接触の危険性があることもわかりました。また、3A棟下の出入り口付近は販売員の人も含めて出入りが多いにも関わらず、急いで通行する自転車も多く、こちらも事故を誘発する空間となっていました。こういった事象を未然に解決することが空間デザインにはあるだろうと感じています。


道路空間としての自転車通行空間整備は2010年頃から大きく変化し、自転車は車道が基本という話が進められ、自転車通行帯などが多くの市町で整備されました。そういった変化に対して、構内では現状維持が続いてきた中で、なにも変わらなくてよいのか。社会の中では快適性・利便性よりも第一に安全性が重視され、投資されます。NYの事例をみれば、大動脈であるからこそ、その動きの活発さ・スピードを維持するのではなく、その多様な人の動きがある中で、より遅い交通に着目し、多くの人に安全で長居できる空間を提供することで、場所の価値・周辺の価値を高めることができる。これは公共や都市の役割でもあるかもしれません。
10月の社会実験を振り返りつつ、まだ途上ではある今後のプロジェクトにむけた議論を進めていきたいと思います。
Other news
↑